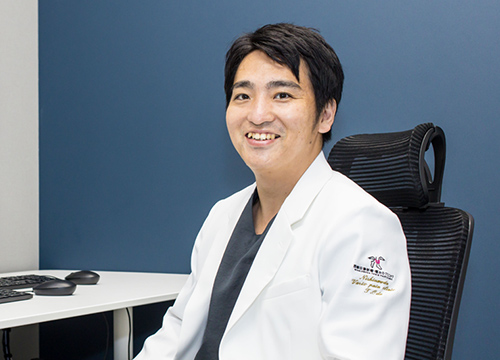足の血管が浮き出ていたり、夕方になると足がむくんだり、だるくなったりする症状はありませんか?もしかしたら、それは下肢静脈瘤かもしれません。
下肢静脈瘤は足の静脈内で発生する血流の停滞や逆流などが原因で、足の血管のぼこぼこした拡張や足のだるさ、足のつり(こむら返り)などを伴う病気です。治療が必要だと感じても、「どの診療科に行けばいいのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
下肢静脈瘤とは?症状と原因
下肢静脈瘤は、足の静脈にある逆流防止弁が壊れることにより、血液が逆流し、血管が拡張・蛇行してコブのように浮き出る病気です。特にふくらはぎ・すね・太ももの内側に多く見られます。
通常、静脈弁は血液が心臓へ戻るときに逆流しないようにする働きをしていますが、加齢・妊娠・立ち仕事などで弁が壊れると、血液が下へ逆流し、血管が圧迫されて変形してしまいます。
主な症状には、足の重だるさ、夕方以降のむくみ、夜間や明け方のこむら返り、皮膚の色素沈着や湿疹などがあります。進行すると皮膚潰瘍を引き起こすこともあるため、症状に気づいたら早めに医療機関を受診することをお勧めします。
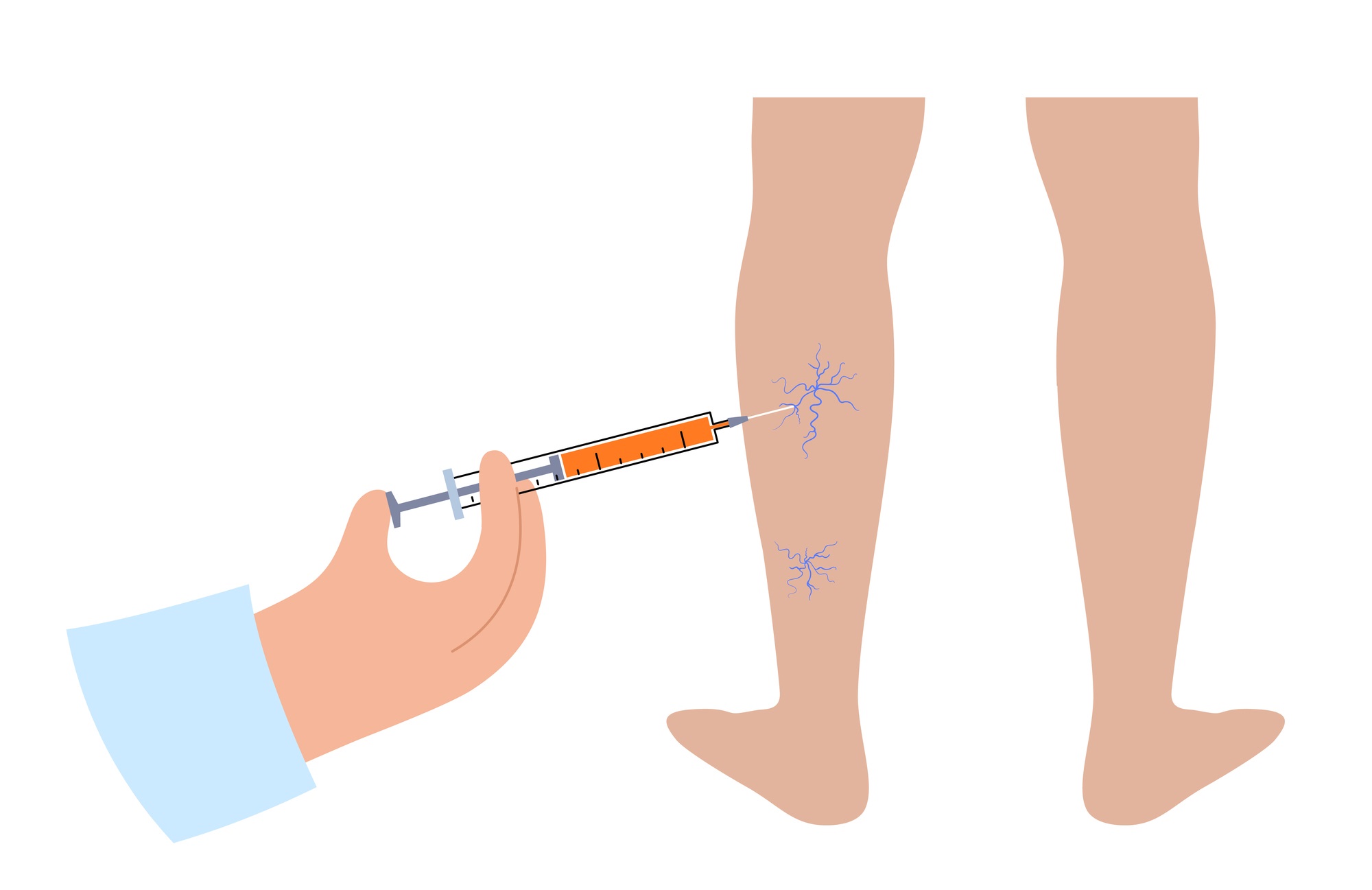
下肢静脈瘤は何科で受診すべき?
下肢静脈瘤の治療は複数の診療科で行われています。それぞれの診療科の特徴を理解して、自分の症状や希望に合った医療機関を選びましょう。
1. 血管外科・心臓血管外科
下肢静脈瘤の診療・治療を最も多く取り扱っている専門診療科です。血管を専門的に扱う診療科なので、下肢静脈瘤の治療においても豊富な経験と知識を持っています。
特にレーザー治療・高周波治療・血管内塞栓術(グルー治療)などの最新の血管内治療を受けたい方は、血管外科または心臓血管外科を受診するのが確実です。
血管外科・心臓血管外科で下肢静脈瘤治療を受ける最大のメリットは、カテーテル治療以外の不全穿通枝に対する切離術や高位結紮術、ストリッピング手術などの外科的治療も得意としているところです。
2. 放射線科(IVR科)
放射線科のIVR医は全身の画像診断のみではなく、X線や超音波などを用いて全身のカテーテル治療を得意とする診療科です。

「カテーテル」を用いた治療は、放射線科のIVR部門で行われることが多く、循環器内科医が得意とする心臓や下肢動脈のカテーテル治療は、非常に繊細な手技を要求されることから、手技的に容易な下肢静脈瘤のカテーテル治療も循環器内科の医師が行うことが多くなってきています。
放射線科で下肢静脈瘤の治療を受けるメリットとしてはカテーテル治療に対する治療実績や使用する接着剤などの知識が豊富であること、治療前後のリスクマネジメントが可能な点が挙げられます。
3. 皮膚科・形成外科
皮膚に湿疹・色素沈着・潰瘍といった皮膚トラブルが主症状の場合には、皮膚科や形成外科での初期診断や処置が行われることがあります。
クモの巣状静脈瘤など皮膚の美容上の問題に対する処置には経験が多く、「皮膚照射レーザー治療」を行なっている施設もあります。そのため、下肢静脈瘤の治療だけでなく、治療後の美容面でもこだわりのある方には、下肢静脈瘤の治療を行なっている形成外科や皮膚科の受診をおすすめすることもあります。
下肢静脈瘤専門クリニックの増加
近年、下肢静脈瘤を専門に扱う医療機関が全国的に増えてきました。都道府県に1つはあると言っても過言ではありません。
下肢静脈瘤専門クリニックでは、下肢静脈瘤の治療に特化した設備や技術を持ち、様々な治療法を提供しています。専門クリニックを選ぶことで、より専門的な治療を受けられる可能性が高まります。

ですから、最近の病院は、ほとんどがホームページを持っていますので、「自分が住んでいる都道府県や市町村名」と「下肢静脈瘤」という2つのキーワードでインターネット検索されるとよいでしょう。
もし近隣になくても、長期の通院は必要ありませんので、多少遠方でも来院を検討してはいかがでしょうか。
専門クリニック選びのポイント
下肢静脈瘤専門クリニックのなかでもいくつか候補がある場合、どうやって選べばよいのでしょうか。ここで、3つのポイントをご説明します。
1つ目は、実際に治療を受けた人に聞くことです。下肢静脈瘤は、発症する人が非常に多い病気ですから、親族や知人に手術を受けたことがある人がいる可能性は高いです。そういった人に術後の調子は良好か、良好な場合はそのクリニックを教えてもらえば確実です。
2つ目は「かかりつけ医に聞くこと」。これも確実です。かかりつけ医がなくても、風邪やほかの病気で病院にかかったときに医師に聞くのがよいでしょう。
3つ目は「医師の話を聞いて決める」ことです。下肢静脈瘤の進行は、非常にゆっくりです。また、悪性の病気でもありませんので治療を急ぐ必要はありません。実際にクリニックで診察や検査をして、最終的には医師の説明に納得してから治療に踏み切るかどうかを決めるのがよいでしょう。
専門医を選ぶ際のポイント
治療を検討する際は、以下の点を参考に信頼できる医師・医療機関を選びましょう。
1. 専門資格・実績
下肢静脈瘤の治療を安心して任せられる医師かどうかは、専門資格と実績で判断できます。「日本IVR学会専門医」「下肢静脈瘤血管内治療指導医」の資格を有しているかを確認しましょう。
また、年間の手術件数や、その医師が何年にわたって静脈瘤治療に携わってきたかという経験年数も信頼の目安になります。
2. 治療の選択肢が豊富か
静脈瘤の状態や患者さんの生活スタイルによって、適した治療法は異なります。レーザー治療や高周波治療といった血管内焼灼術、接着剤を用いたグルー治療、硬化療法、ストリッピング手術など、複数の選択肢から最適な治療を提案してくれる医師を選びましょう。
1つの治療法しか提供していない場合、柔軟な対応が難しいケースもあります。
3. 初診時の説明やカウンセリング
初診時には、超音波検査などを用いた的確な診断が行われ、治療の必要性や選択肢について丁寧に説明してくれるかを確認しましょう。
患者の気持ちに寄り添い、納得できるまで説明してくれる医師は信頼できます。「診察5分で即手術決定」など、一方的な提案をする場合には注意が必要です。セカンドオピニオンを求めるのは患者の当然の権利です。納得できるまで複数の医師に相談するのも良い判断です。
4. 術後フォロー体制
下肢静脈瘤の治療後は、定期的な経過観察が重要です。術後のフォローアップ体制が整っているかどうかも、医療機関選びの重要なポイントになります。
治療後に何か問題が生じた場合の対応方針や、再発時の対応についても事前に確認しておくと安心です。
西梅田静脈瘤・痛みのクリニックでの下肢静脈瘤治療
大阪梅田に位置する西梅田静脈瘤・痛みのクリニックは、血管外科と整形外科を専門とする医療機関です。日本IVR学会専門医、下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医・実施医、脈管学会専門医の資格を持つ医師による専門的な治療を提供しています。
下肢静脈瘤の治療として、カテーテル治療、高周波カテーテル治療、グルー治療、ストリッピング手術、高位結紮術、硬化療法などの日帰り手術に対応しています。患者の病態やニーズに合わせた治療法を選択し、日常生活への影響を最小限に抑えながら症状の改善・解消を目指します。
クリニックは大阪駅と福島駅の中間に位置し、両駅から徒歩約5分というアクセスの良さが特徴です。平日は18時まで、土曜日も9:00~13:00まで診療を行っており、仕事で忙しい方でも通院しやすい環境を整えています。
2025年6月現在、女性医師による診察・手術も可能となり、より多様なニーズに対応できる体制を整えています。
まとめ:下肢静脈瘤の適切な診療科選び
下肢静脈瘤の治療は、血管外科・心臓血管外科、放射線科、皮膚科・形成外科など複数の診療科で行われています。それぞれの診療科には特徴があり、患者さんの症状や希望に合わせて選ぶことが大切です。
確実な診断と適切な治療を受けるには、下肢静脈瘤の治療実績が豊富な心臓血管外科や血管外科を受診するのが最も安心です。また、近年増加している下肢静脈瘤専門クリニックも選択肢の一つとして考えられます。
専門医を選ぶ際は、専門資格・実績、治療の選択肢の豊富さ、初診時の説明やカウンセリングの質、術後フォロー体制などをポイントに検討しましょう。
下肢静脈瘤は放置すると症状が進行する可能性がありますが、適切な治療を受ければ症状の改善が期待できます。少しでも気になる症状があれば、専門医に相談することをお勧めします。
大阪梅田エリアで下肢静脈瘤の治療をお考えの方は、西梅田静脈瘤・痛みのクリニックにご相談ください。血管外科の専門医による最適な治療をご提案いたします。詳しくは西梅田静脈瘤・痛みのクリニックのホームページをご覧ください。
【著者】
西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック 院長 小田 晃義
【略歴】
現在は大阪・西梅田にて「西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック」の院長を務める。
下肢静脈瘤の日帰りレーザー手術・グルー治療(血管内塞栓術)・カテーテル治療、再発予防指導を得意とし、
患者様一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド医療を提供している。
早期診断・早期治療”を軸に、「足のだるさ・むくみ・痛み」の原因を根本から改善することを目的とした診療方針を掲げ、静脈瘤だけでなく神経障害性疼痛・慢性腰痛・坐骨神経痛にも対応している。
【所属学会・資格】
日本医学放射線学会読影専門医、認定医
日本IVR学会専門医
日本脈管学会専門医
下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医、実施医
マンモグラフィー読影認定医
本記事は、日々の臨床現場での経験と、医学的根拠に基づいた情報をもとに監修・執筆しています。
インターネットには誤解を招く情報も多くありますが、当院では医学的エビデンスに基づいた正確で信頼性のある情報提供を重視しています。
特に下肢静脈瘤や慢性疼痛は、自己判断では悪化を招くケースも多いため、正しい知識を広く伝えることを使命と考えています。