はじめに
足の血管が浮き出て見た目が気になる、足がだるい、むくみやこむら返りが起こる……。これらは、下肢静脈瘤の典型的な症状です。症状が進むと、皮膚の変色や潰瘍など、日常生活に支障をきたすこともあります。
近年、下肢静脈瘤に対する手術治療は大きく進化し、患者さんの負担を軽減しながら効果的に症状を改善できるようになってきました。しかし、治療法が多様化したことで「自分に最適な方法はどれか」と迷う方も多いのではないでしょうか?
この記事では、現在主に行われている4つの手術療法を比較し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。あなたに合った治療法を見つけるための参考にしてください。
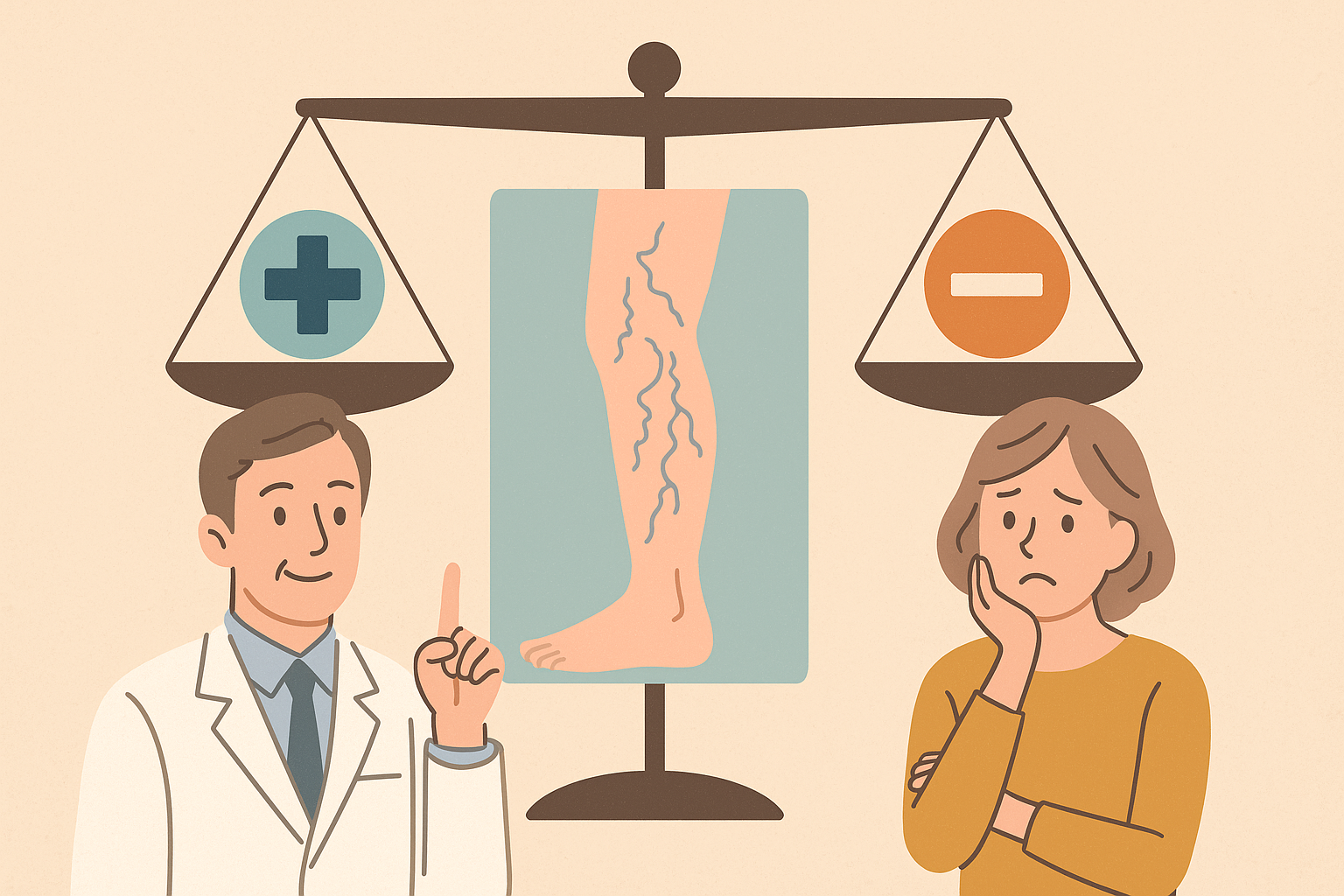
下肢静脈瘤とは? ~症状と原因を理解しよう
下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、足の静脈に見られる比較的よくある疾患で、主に静脈内にある「弁」の機能が低下することにより発症します。通常、足の静脈には血液が重力に逆らって心臓に戻るように流れを調整する「逆流防止弁」が備わっています。しかし、この弁がうまく閉じなくなると、血液が本来とは逆方向に流れてしまい、血管内に血液が溜まりやすくなります。
この血液の滞留が続くと、静脈が異常に膨らんでしまい、皮膚の表面から「こぶ」のように浮き出て見える状態になります。これが、いわゆる「静脈瘤(じょうみゃくりゅう)」と呼ばれるものです。
下肢静脈瘤の初期には、見た目に目立つ症状がない場合もありますが、進行するにつれて足のだるさや重さ、むくみ、就寝中のこむら返り(足のつり)などの不快な症状が現れることがあります。さらに、皮膚にかゆみや変色、湿疹、重度の場合は潰瘍ができるなど、皮膚症状としてあらわれるケースもあります。
発症の主な原因は、加齢や遺伝、長時間の立ち仕事・座り仕事などによる血流の停滞ですが、妊娠や出産をきっかけに発症する方も少なくありません。特に女性に多く見られる疾患のひとつです。
下肢静脈瘤は命に関わるような病気ではありませんが、見た目の変化や不快な症状によって生活の質を大きく低下させることがあります。早期に異変に気づき、適切な診断と治療を受けることで、症状の進行を防ぎ、快適な生活を取り戻すことができます。
主な症状:
足の血管がボコボコと浮き出て目立つ、足がだるい・重い・むくむといった違和感、夜中や明け方に突然起こるこむら返り(足のつり)、さらにかゆみや皮膚の変色、ひどくなると潰瘍を伴うような皮膚トラブル——こうした症状に心当たりがある方は、下肢静脈瘤の可能性が考えられます。初期の段階では見た目の変化や軽い疲労感だけのこともありますが、放置しているうちに徐々に症状が進行し、痛みや皮膚の異常など、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。
特に注意が必要なのが、長時間の立ち仕事・座り仕事に従事している方や、妊娠・出産を経験された女性、年齢とともに血管の弾力が低下しやすい中高年の方です。これらの条件は血流の滞りを引き起こしやすく、下肢静脈瘤の発症リスクを高める要因とされています。
下肢静脈瘤自体は命に関わる病気ではないものの、「見た目が気になる」「足の疲れが取れにくい」「皮膚が黒ずんできた」などの問題を抱えながら我慢してしまう方も多くいらっしゃいます。症状が進行すると、湿疹や色素沈着、難治性の潰瘍といった皮膚トラブルに悩まされることもあるため、早めの診断と治療が非常に重要です。
近年では、日帰りで受けられる低侵襲の治療法も普及しており、身体への負担を最小限に抑えながら症状の改善を目指すことができます。「まだ受診するほどではない」と感じていても、気になる症状がある場合は、一度専門医の診察を受けてみることをおすすめします。早期に対応することで、将来的な悪化を防ぎ、より快適な日常生活を送ることができるでしょう。
手術療法の種類と特徴
現在主流の手術療法は次の4つです。
1. 血管内焼灼術(レーザー/高周波)
細いカテーテルを静脈に挿入し、熱(レーザーまたは高周波)を用いて血管を内側から焼灼・閉塞します。日帰り手術が可能で、現在もっとも広く行われている治療法です。
2. 血管内塞栓術(グルー治療)
熱を使わず、接着剤(医療用グルー)をカテーテルから注入して静脈を閉塞します。痛みや圧迫療法の負担が少ないのが特徴で、2019年より保険適用になった新しい治療法です。
3. ストリッピング手術
切開して静脈を物理的に引き抜く従来型の外科手術。全身または下半身麻酔が必要で入院を要することもありますが、特定の症例には有効です。
4. 硬化療法
硬化剤(薬剤)を注入して静脈を閉塞させる方法。外来で行え、比較的簡単ですが、再発率が高く小さな静脈瘤に限定されます。
各治療法のメリット・デメリット比較
|
治療法 |
メリット |
デメリット |
|
血管内焼灼術 |
傷跡が小さい/再発率が低い /日帰り可 |
術後のストッキング着用/一時的な痛みや腫れ |
|
グルー治療 |
圧迫療法不要/熱を使わず痛みが少ない/傷跡が小さい /再発率が低い/日帰り可 |
接着剤によるアレルギー/治療費がやや高い |
|
ストリッピング |
確実な除去/長期実績あり |
傷跡・痛みが大きい/入院や麻酔が必要/神経障害のリスクが高い |
|
硬化療法 |
外来で簡単に実施/費用が安い |
再発しやすい/色素沈着や潰瘍の可能性 |
治療法の選び方 ~あなたに合った選択を
症状の程度で選ぶ
・根本的な治療:焼灼術もしくはグルーが
・ごく一部の再発症例:ストリッピング
・再発性静脈瘤、側枝型静脈瘤、蜘蛛の巣血管:硬化療法
生活スタイルで選ぶ
- ・仕事復帰を急ぐ方:焼灼術・グルー治療が有利です
- ・ストッキングが負担な方:グルー治療がおすすめです
医師の専門性で選ぶ
IVR専門医、心臓血管外科専門医、脈管専門医を有し、なおかつ血管内焼灼術指導医の資格のある医師だと専門性高い下肢静脈瘤治療が期待できる可能性が高いです。
手術後の経過と生活上の注意点
術後の経過(目安)
- 焼灼術・グルー治療:翌日から日常生活可/違和感は1~2週間程度
- ストリッピング:回復に1〜3週間必要/痛みや腫れも強め
- 硬化療法:処置後すぐ歩行可/数日間は色素沈着に注意
術後の注意点
- 弾性ストッキングの着用(医師の指示による)
- 適度な運動と休息のバランス
- 長時間の同姿勢を避ける
- 水分補給と体重管理
- 禁煙と定期検診
今後の展望 ~治療はさらに進化する
下肢静脈瘤の治療は、ここ数年で大きな進歩を遂げてきましたが、今後さらに発展していくと予想されています。キーワードとなるのは、「低侵襲(ていしんしゅう)な手術」「個別化医療(テーラーメイド医療)」「予防医学」です。
これまでも身体への負担が少ない日帰り手術やレーザー治療が普及してきましたが、今後はさらに痛みやダウンタイムを最小限に抑える「より低侵襲な手術」が主流になっていくでしょう。たとえば、血管内に使用する接着剤の改良や、より細くて柔軟なカテーテルの開発が進んでおり、治療精度の向上と患者の快適性が同時に実現されつつあります。
また、患者一人ひとりの体質や生活環境に応じた「テーラーメイド医療」も今後の中心的なテーマとなります。単に血管を処置するだけでなく、その人の生活スタイルや仕事の特性、既往歴などを踏まえて治療計画を立てることで、より高い満足度と長期的な効果が期待できるようになります。
さらに重要なのが、「再発を防ぐ」ための取り組みです。治療後も、正しい生活習慣や姿勢の見直し、適切な運動の継続が欠かせません。今後は、医師による予防教育の強化や、患者自身が日常生活の中で意識できるセルフケアの指導なども、医療の一環としてますます重視されるようになるでしょう。
このように、下肢静脈瘤治療は「治す医療」から「再発を防ぎ、快適に暮らすための医療」へとシフトしています。症状のある方はもちろん、再発リスクを抱える方にとっても、今後ますます希望の持てる時代が訪れようとしています。
まとめ ~最適な治療で快適な足を取り戻す
静脈瘤手術は、技術の進歩により負担が少なくなり、多くの方が日帰りで治療を受けられる時代になっています。重要なのは、自分の状態に合った治療を選ぶこと。
西梅田静脈瘤・痛みのクリニックでは、経験豊富な医師が患者一人ひとりに合わせた治療を提案。手術後のサポート体制も整っており、安心して治療を受けることができます。
足の症状が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

【著者】
西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック 院長 小田 晃義
【略歴】
現在は大阪・西梅田にて「西梅田 静脈瘤・痛みのクリニック」の院長を務める。
下肢静脈瘤の日帰りレーザー手術・グルー治療(血管内塞栓術)・カテーテル治療、再発予防指導を得意とし、
患者様一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイド医療を提供している。
早期診断・早期治療”を軸に、「足のだるさ・むくみ・痛み」の原因を根本から改善することを目的とした診療方針を掲げ、静脈瘤だけでなく神経障害性疼痛・慢性腰痛・坐骨神経痛にも対応している。
【所属学会・資格】
日本医学放射線学会読影専門医、認定医
日本IVR学会専門医
日本脈管学会専門医
下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医、実施医
マンモグラフィー読影認定医
本記事は、日々の臨床現場での経験と、医学的根拠に基づいた情報をもとに監修・執筆しています。
インターネットには誤解を招く情報も多くありますが、当院では医学的エビデンスに基づいた正確で信頼性のある情報提供を重視しています。
特に下肢静脈瘤や慢性疼痛は、自己判断では悪化を招くケースも多いため、正しい知識を広く伝えることを使命と考えています。



